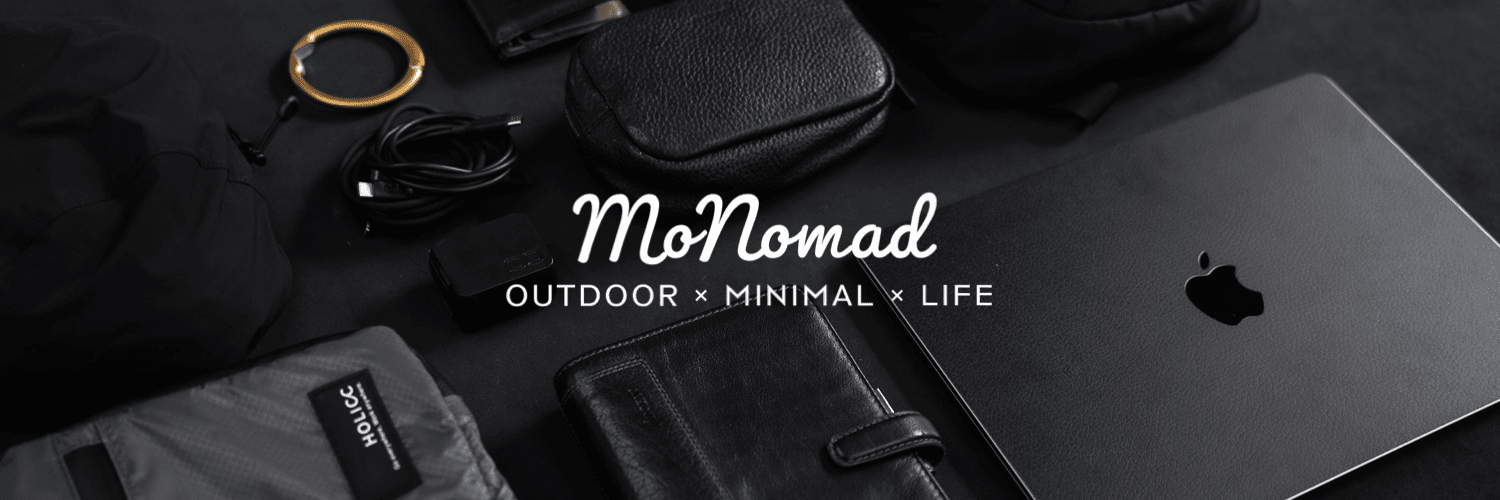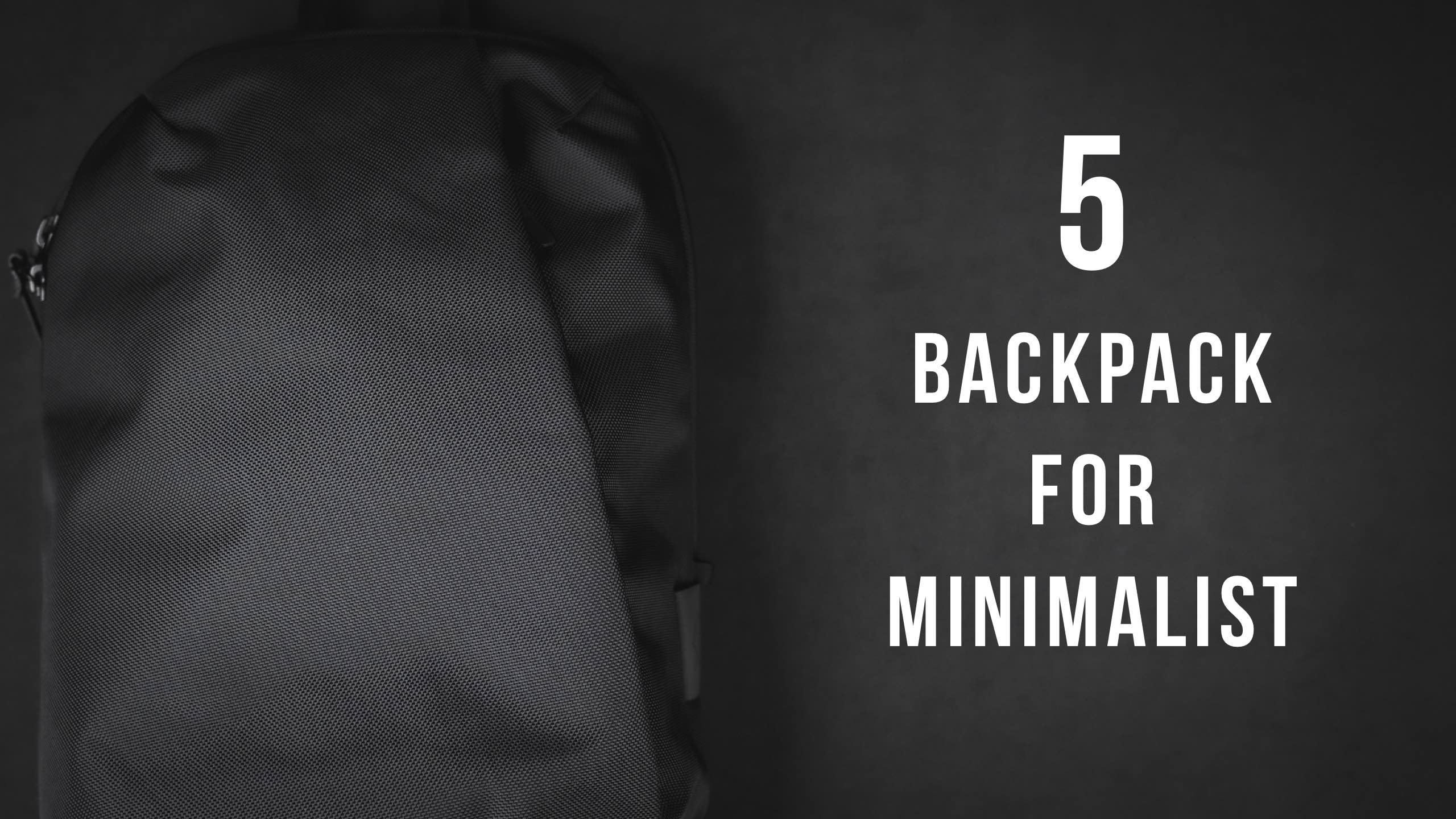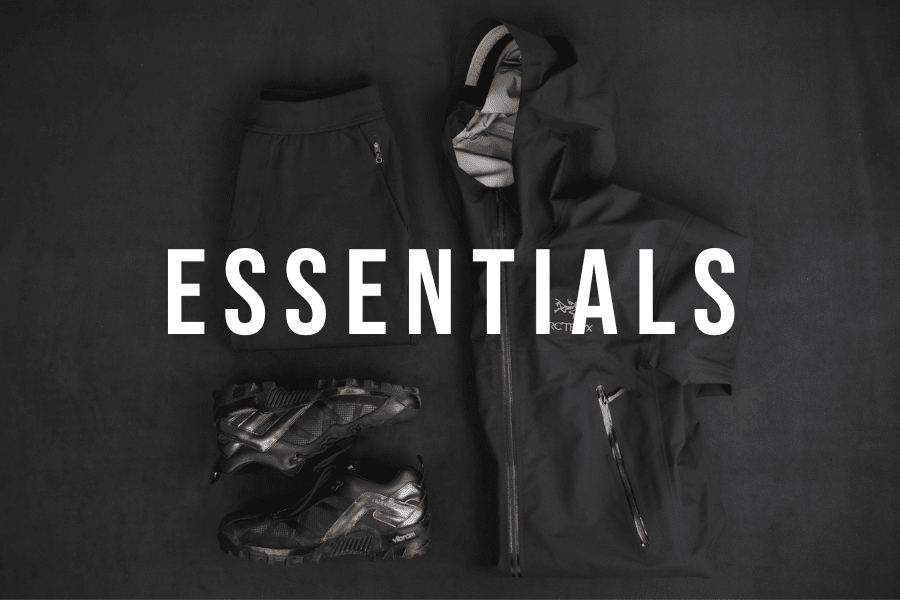【地方移住】どうして山奥の限界集落へ?Part.2【Inside #4】

Part.1の続きから。
前回記事はこちら↓

選んだのは第3の選択肢
③なにかの縁や仕組みにより、外部人材として活動する
結局選んだのは3つ目の選択肢。
最も不確実性が高くリスクの塊ですが、将来性もありました。
個人クリエイターでも転職でもない、企業や事業者との関わり方です。
いきなり縁もゆかりもない土地に移住して、そんな活動ができるのか?
そもそも外部を頼ったり、ましてやデジタル分野のコンサルなんて存在しない仕事なので、絶対に無理です。
ただ、時代も変わりつつあります。
都市部の人材や外部のノウハウを地方に取り入れるための仕組みが着実に増えてきています。
地方とのきっかけをつくる仕組みを活用
急によそ者が移住してきて、「コンサルできます!」「カメラできます!」「HPつくれます!」と叫んだところで当然信用されない。
そのきっかけづくりとして国の制度を活用しました。
当時候補として考えていたのは、上の2つ。
もともと地域にしっかりと入り込んでやりたかったし、そうでないと地方創生が実現しないことを前職時代に体感していたので、「地域おこし協力隊」を選択しました。
総務省の制度。都市部から地方への若者の移住を目的に、地場産品の開発やブランドのPR、移住促進など、地域の課題解決を図る取り組み。最長で3年の人気があり、任期中は各自治体からの報酬が発生する。
簡単に言うと、3年間は猶予あげるから、その間に食い扶持見つけてね!という制度です。
実際にはその期間に土壌を作り、活動内容を活かして事業ができるような人は少なく、地域の中で就職したり、そのまま公務員として採用されたりすることが大半。
一昔前は自力で起業できるような人はほぼいなかったし、自治体の受け入れ体制も整っていませんでしたが、徐々に変わりつつあります。
限界集落へ地方移住した理由
記事のタイトルにもある質問の答えは
本当に自分がやり続けたいライフワークに出会える可能性が高かったから
具体的には、地域おこし協力隊を活用し、地域とマッチングするきっかけをもらい、自分の事業で独立する。
ほかにライフスタイルの価値観なども理由としてありますが、1番は仕事です。
よく地方移住とか、山に暮らすと言うと、FIREしてゆったりと暮らすとか、スローライフ的なイメージが強いですが、自分の場合はまったく逆。
仕事から脱出するではなくて、やりたい仕事をするための選択でした。
移住して結果どうなったのか、次回の記事で書きたいと思います。
引き続き #insideで裏側についてまとめていきますので、ぜひまたご覧ください。